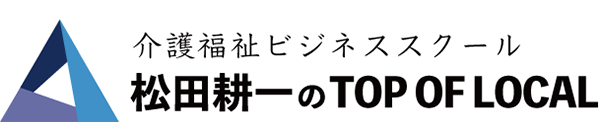第303回はいただいた質問に対して、松田耕一が回答します。
はじめまして。私は関西エリアで介護福祉事業を運営しております。
いつもPodcastを拝聴し、大変勉強させていただいております。今回、スタッフの定着率に関して深刻に悩んでおりまして、特に「入職して半年ほどで“辞めたい”という声が上がる原因を、どのように分析すればよいのか」について、ぜひ番組でアドバイスをいただきたくご連絡いたしました。
当事業所では、給与や待遇面だけでなく、研修制度やメンタルサポートの充実を図っているつもりですが、それでも半年ほどたつと退職を考えるスタッフが一定数いるのが現状です。スタッフそれぞれが感じている不満や悩みがどこにあるのか、経営者として何を見落としているのか……そのあたりを掘り下げていただけると大変助かります。
スタッフ一人ひとりがやりがいを持って長く働けるよう、職場環境をより良くしたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。